会報バックナンバーより
八ッ場あしたの会について
会報バックナンバーより
八ッ場あしたの会では、数ヶ月に一度、会報を発行し、八ッ場ダム問題やダム事業についての情報を発信しています。
会報は会員のほか、カンパを振り込んで下さった方や、集会に参加された方にも送っています。
会報No.1より:巻頭言
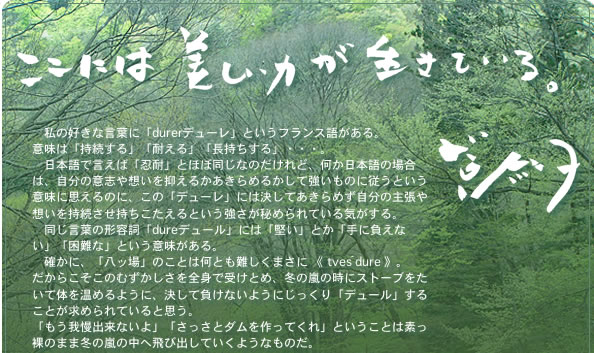
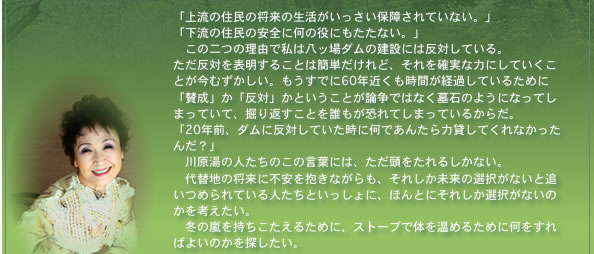
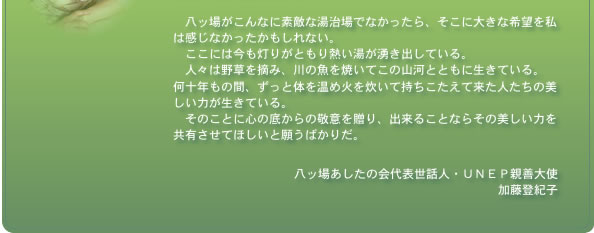
会報No2より
「渓ばたの温泉」河野千絵 (短歌同人誌「場の会」より)
若山牧水の紀行文「渓ばたの温泉」(「静かなる旅をゆきつつ」所収)は十一頁ほどの掌編であるが、その内のおよそ半分が吾妻渓谷の描写に充てられている。牧水は、この渓谷には以前「甚だしく感興をそゝられた」ゆえに、今回は新緑の季節を撰んで再び同地を訪れ、一週間余りの滞在の日々を散策にいそしんだ。
この文章の中の圧巻は、渓谷を奔る吾妻川の描写であろう。折しも雨の多い若葉の候、増水した川の勢いは強い。牧水は言葉を尽くして水の動きを追う。まるで彼自身が川の流れの一部となって両岸を穿ち、岸壁を洗い、飛沫をあげつつくるくる渦巻きながら岩の間を流れ下ってゆく、その実況中継をするかのごとき臨場感だ。躍動する美しい渓谷の姿を、その威勢のままに筆で丸ごと写し取っているような迫力である。正直、この場面は牧水の興奮ぶりにいささか気圧されもする箇所ではある。が、難所をくぐり終えて息をつくように速度を抑えつつ、渓谷の森の奥から湧き出して岩の間を下る細い寂しい「あるかなきかの夢のやうな瀧に對ってゐると、心の底に沈んでゐた人間の寂しさやものなつかしさがあからさまに身體を浸して来るのを覺えがちである。」と彼が続けて語る時、牧水の歌の数々が人々に愛唱されている理由を垣間見るような気持ちになる。
ところで、「渓ばたの温泉」について語るには、次の箇所を措くわけにはいかない。「私はどうかこの渓間の林がいつまでもいつまでもこの寂びと深みとを湛えて永久に茂つてゐて呉れることを心から祈るものである。ほんとに土地の有志家といはず群馬縣の當局者といはず、どうか私と同じ心でこのさう廣大でもない森林のために永久の愛護者となつてほしいものである。」
この切実な危機感はどうだろう。牧水は既にこの時点で、新緑の渓谷の景観に胸を躍らせる一方、思いがけなくも悲痛な危惧を抱いている。実際に、彼が身を絞る思いで存続と保護を祈ってからほんの八十年余りを経た現在、まさしくこの渓間の林でダム建設工事の樹木伐採が進み、山肌が次々に削られていることを思うと、私はつくづく情けなく申し訳なく、やりきれなさで胸が塞がる。ダムの名前は八ッ場ダムという。
牧水が吾妻渓谷を訪れ、この紀行文を書いたのは大正九年のことである。大正初期から日本は、本格的なコンクリートダム建設の時代に入っていった。むろん、八ッ場ダムの建設計画を牧水が予測していたとは思えない。牧水のこの哀切極まりない危機意識は、それからの日本の自然が辿らされる運命に図らずも寄り添ったものであり、当時の時代状況の中で彼が抱いた、本能的な直感であったのだろう。
文学でも美術でも、およそ芸術に関わる人の心は自然について無関心でいられないというのが、私の考えである。特に短詩型の文学においては、自然との関わりを拓く回路によって作品の生命の長さが決まると思う。千本松原の伐採計画に反対し、熱筆をふるった牧水を私は尊敬する。彼の自然への直情的な傾斜を、私は讃える。無条件に自然へ引き寄せられ、その交歓を享受できた時代は、しかし、既に喪われてしまった。同時に、文学も大きな拠を喪ってしまったという重い現実を軸に、私は堂々巡りをしている。
