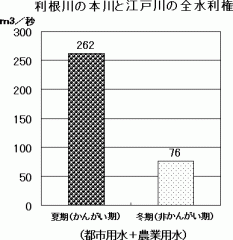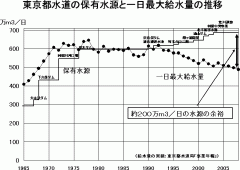マスコミ報道の誤り―III.八ッ場ダムの暫定水利権がダム中止に伴って失われるという話の誤り
マスコミ・行政の問題
マスコミ報道の誤り
(2009年9月17日)
II.八ッ場ダムはすでに7割もできているという話の誤りについて
III.八ッ場ダムの暫定水利権がダム中止に伴って失われるという話の誤り
IV.大渇水到来のために八ッ場ダムが必要だという話の誤り
V.八ッ場ダムは利根川の治水対策として重要という話の誤り
VI.ダム予定地の生活再建と地域の再生について
III.八ッ場ダムの暫定水利権がダム中止に伴って失われるという話の誤り
1.八ッ場ダムの暫定水利権は長年の取水実績があり、支障を来たしたことがない。
八ッ場ダムの暫定水利権とは、八ッ場ダムの先取りの水利権として暫定的に許可された水利権のことで、そのほとんどを占めるのが埼玉県や群馬県などの農業用水転用水利権の冬期の取水である。農業用水を転用した水利権であるから、冬期は権利がないとされ、八ッ場ダム事業への参加で冬期の水利権を得ることが求められている。しかし、これらの農業用水転用水利権は夏期も冬期も長年の取水実績がある。古いものは37年間も取水し続けている。その間、冬期の取水に支障を来たしことがない。
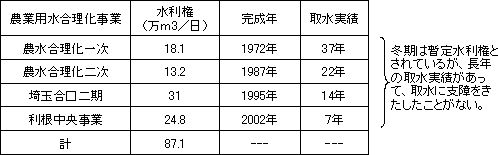
2.利根川の冬期は取水量が激減するので、水利用の面で余裕がある。
利根川の冬期は夏期よりも流量が少ないが(冬期の晴天日の流量は夏期の6割程度)、農業用水の取水量が激減するので(冬期の都市・農業用水の全取水量は夏期の3割程度、左下の図)、水利用の面でも十分な余裕がある。それを反映して、利根川では冬期の渇水はきわめてまれである。過去において冬期に取水制限が行われたのは平成8年と9年の冬だけである。その取水制限率は10%であって、ほとんど自主節水にとどまっており、生活への影響は皆無であった。平成8、9年当時と比べて現在は首都圏の保有水源が増えていることと、取水量が減少してきていることもあり(右下の図)、八ッ場ダムなどなくても、埼玉県水道等の農業用水転用水利権が冬期の取水を続けることに何の問題もない。
3.ダム中止後も継続される暫定水利権
今まで数多くのダムが中止されてきている。その中には、中止されたダムの完成を前提とした暫定水利権がそのダムの利水予定者に許可されていたケースがあるが、ダム中止後にその暫定水利権が消失することはなく、そのままの使用が認められている。具体的な例としては、徳島県の細川内ダムや新潟県の清津川ダムがある。両ダムとも国土交通省のダムである。八ッ場ダムの暫定水利権がダム中止後、使用できなくなることは決してない。
- 細川内ダム(徳島県、国土交通省) 2000年度に中止
- 暫定水利権は那賀町工業用水道で、現在も継続使用
- 清津川ダム(新潟県、国土交通省) 2002年度に中止
-
暫定水利権は周辺9市町村の水道で、ダム中止後も継続使用。
その後、市町村合併により、水源の融通がなされ、2006年度までに清津川ダムの暫定水利権は解消されている。
4.埼玉県民の過重負担
埼玉県水道を例にとれば、農業用水転用水利権の確保のため、すでに多額の費用を負担している。利根中央事業の場合は1m3/秒あたりの負担額が125億円にもなっている。八ッ場ダムの非かんがい期(冬期)の水利権に対する同県の負担額は約74億円であるから、夏期と冬期それぞれ水利権を得るということで、約200億円の負担になっている。
一方、八ッ場ダムで通年の水利権を得る茨城県水道の1m3/秒あたりの負担額は131億円であるから。埼玉県民はその1.5倍以上の負担をさせられつつある。
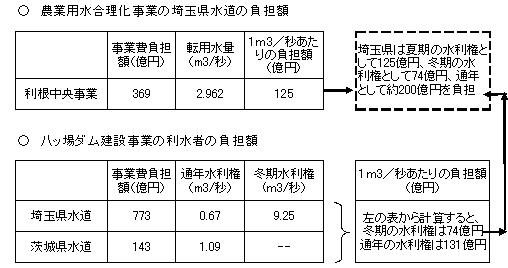
5.水利権の許可権をダム建設推進の手段に使う国交省
上述のとおり、八ッ場ダムの暫定水利権は、八ッ場ダムがなくても取水し続けることが可能なのであるから、安定水利権として認めればよいのだが、利根川の水利権許可権者は国交省で、八ッ場ダム建設の事業者も同じ国交省である。国交省は水利権許可権をダム事業推進の手段に使っていると言ってよい。実態に合わない非合理的な水利権許可行政を根本から改める必要がある。